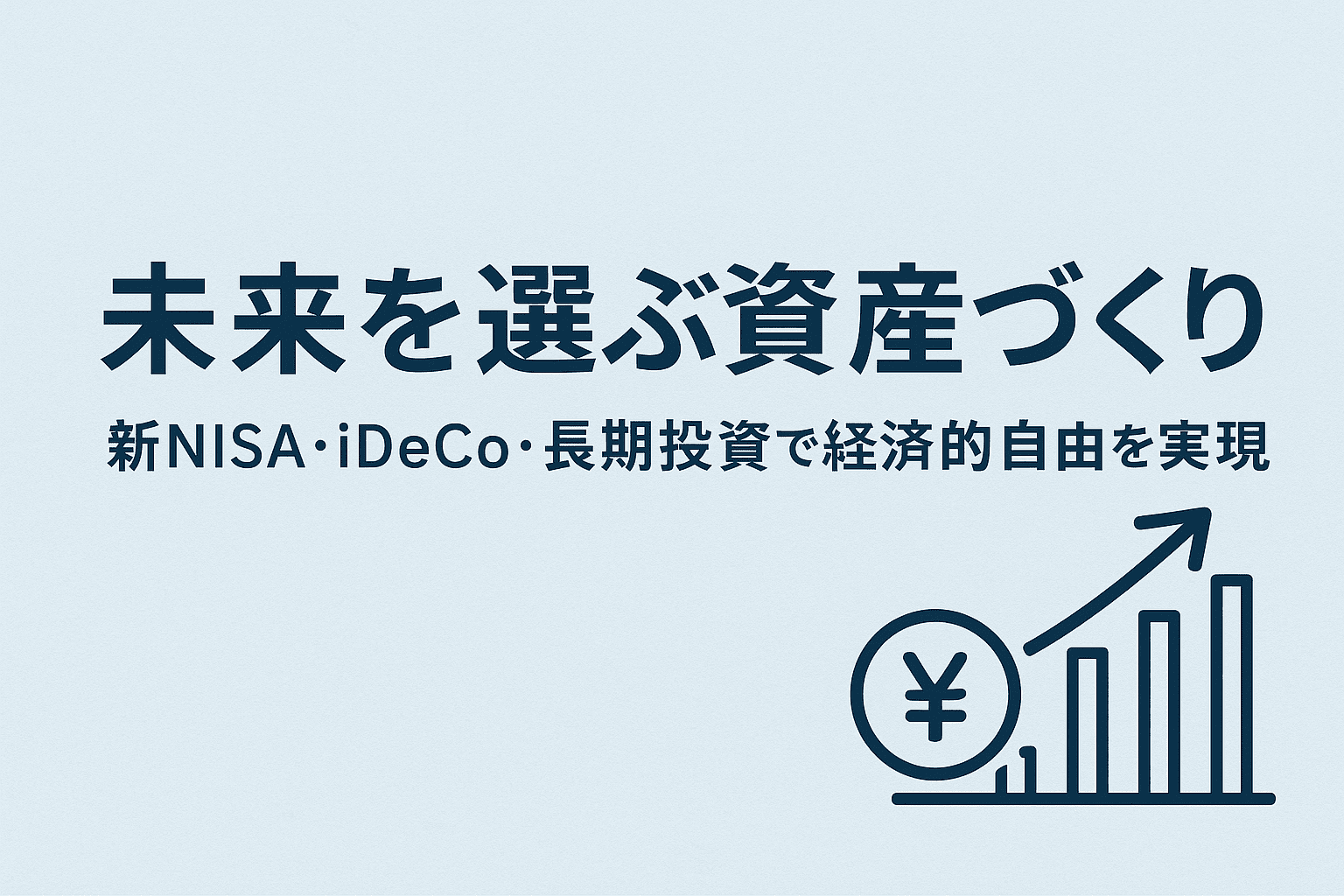はじめに
「お金は貯めるもの」と教えるのは簡単です。でも、本当に大切なのは「なぜ貯めるのか」を理解することではないでしょうか。
子どもにとって“貯金”はまだ遠い存在。だからこそ、「お金は使うためにある」という感覚を、早い段階で育てておくことが、後の金銭感覚を左右します。
“使うために貯める”という考え方を家庭で育てる
お金を貯める目的は、「安心」のためだけではなく、「自分の未来を選ぶ自由」を得るためにあります。
この考えを子どもに伝えるとき、まず大人がその意識を持っていることが大切です。
なぜなら、「お金=我慢の象徴」になってしまうと、使うことに罪悪感を覚えるようになるからです。
一方で「お金=目的を叶える道具」と考えられれば、自然と前向きな選択ができるようになります。
たとえば、「ゲームを買うために貯める」よりも、「夏休みに家族で旅行に行くために貯める」という目標を一緒に立ててみましょう。
“使う目的”を明確にすることで、貯金が「楽しい行動」に変わります。
結果として、子どもは「お金を管理する力」と「先を見通す力」を同時に育てることができるのです。
お金を使うことで得られる“体験”の価値を教える
子どもにとって、モノよりも体験が心に残ります。
貯めたお金で得た体験が、本人の中で「お金=幸せをつくる手段」として記憶されれば、浪費や衝動買いの抑止にもつながります。
親としてできることは、使った後にその体験を一緒に振り返ること。
「このお金で何を感じた?」「次にどんなことに使いたい?」と問いかけるだけで、思考の質がぐっと変わります。
実際、筆者の家庭でも「貯金箱の使い道会議」を月に一度開いています。
子どもたちは自分のアイデアを発表し、「これはいいね」と家族で共感する時間が生まれます。
こうした習慣が、金額よりも“目的意識”を大切にする感覚を育ててくれます。
まとめ
お金の教育は、「貯め方」よりも「使い方」から始めるほうが、実はずっと効果的です。
子どもに「お金は未来をつくる道具」だと伝えれば、貯める行為が目的化することはありません。
大切なのは、貯める=準備、使う=選択、体験=成長という流れを意識させること。
家庭の中で小さな成功体験を積み重ねるうちに、子どもは自然と“お金を生かす人”になっていくでしょう。
今日からできる一歩として、「次に使いたい目的」を家族で話してみませんか。