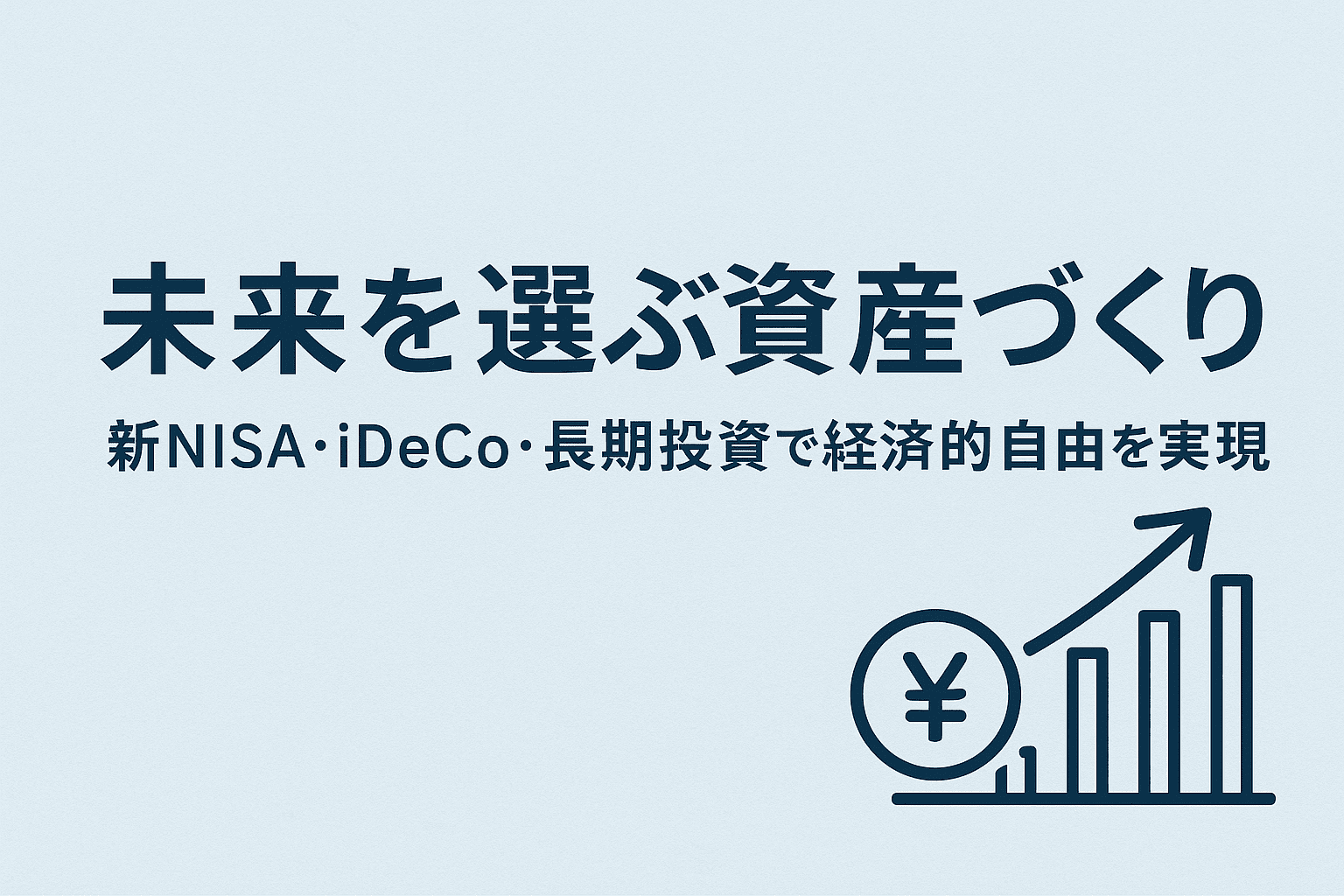はじめに
「もう、やめたい…」
ある日、娘がピアノの前で小さくつぶやきました。
頑張って続けてきたけれど、最近は練習も億劫そう。
親としては「もったいない」と思う反面、無理をさせたくもない——。
その葛藤の中で、私が口にした一言が、家計との向き合い方にもつながるとは思いませんでした。
「やめたい」と言う子どもへの向き合い方
「やめることは、逃げることじゃない。」
そう伝えたのが、最初の一言でした。
子どもが「やめたい」と言うと、親はつい“根性論”で返しがちです。
しかし、本当に大切なのは“続けること”よりも“納得して選ぶこと”だと気づきました。
理由を聞くと、「楽しくなくなった」とのこと。
そこで「じゃあ、どうすれば楽しくなる?」と問い返しました。
一緒に考えることで、本人の気持ちが整理され、やがて「週1回だけ続けたい」と自分で決めました。
「やめない」ではなく、「やめ方を選ぶ」こと。
それが、子どもの自立につながる一歩だったのです。
家計から見える“やめる勇気”
習い事は、家計にとっても小さくない支出です。
月謝が5,000円〜1万円、年間で10万円を超えることもあります。
家計簿の中で“固定費”のように扱ってしまうと、「やめる」判断が鈍ります。
しかし、“習い事も投資”と考えると見え方が変わります。
成果が出ていない投資は、見直しが必要です。
同様に、子どもの気持ちが離れている習い事も、続ける意味を一度リセットする価値があります。
「もったいない」は、感情の言葉。
でも、「使い方を見直そう」は、未来の言葉です。
この違いが、家計を前向きに変えてくれます。
お金と気持ちのバランスをとる
我が家では、習い事を「本人の意思+家計バランス」で判断しています。
本人のやる気が50%以上あるなら続行。
一方で、家計に無理があるなら、一時的に減らしてもOK。
“やめる勇気”も、“続ける覚悟”も、どちらも成長です。
大事なのは、親が「お金の都合」だけでなく、「心の都合」も聞いてあげること。
子どもが何かを「やめたい」と言ったときこそ、家計を見直すチャンス。
そして、家族で“お金の使い方”を考える、最高の学びの時間になります。
まとめ
「やめたい」と言う声は、変化のサイン。
それを否定せずに受け止めることで、親も家計も少し柔らかくなれます。
お金は、我慢のために使うものではなく、選択のために使うもの。
今日の会話が、そんな気づきをくれました。
あなたの家庭にも、「話してよかった」と思える一言がありますように。