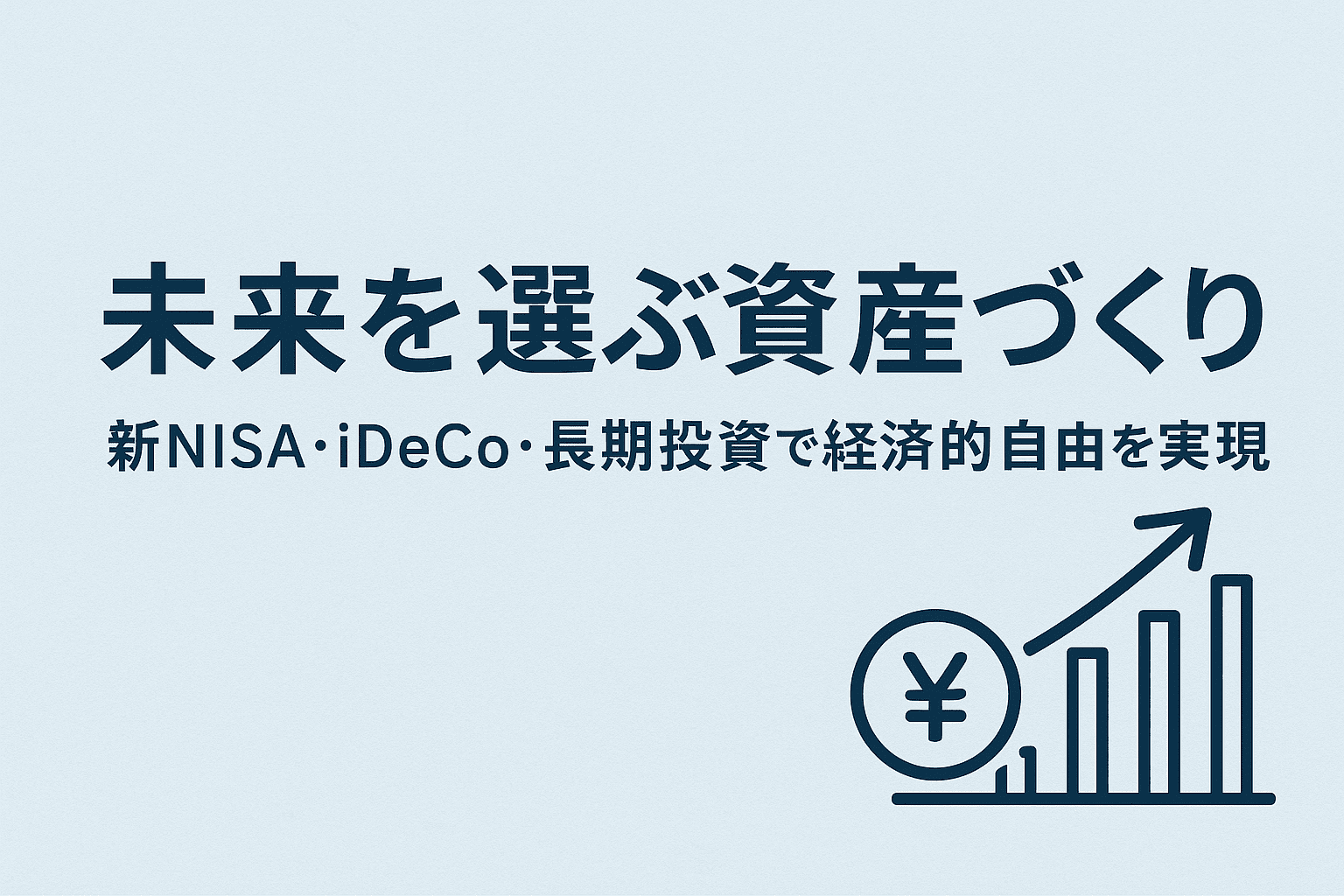はじめに
「家は資産になる」と聞く一方で、「賃貸こそ自由だ」という声もあります。
どちらを選ぶかで、人生のリズムもお金の流れも大きく変わります。
経済的自由を目指すうえで、どちらが有利なのか――。
今回は“数字”と“心の自由”の両面から、この永遠のテーマを考えます。
経済的自由を目指す人が重視すべき視点
結論から言えば、「住宅ローン」か「賃貸」かよりも、**“固定費をどこまでコントロールできるか”**がカギです。
経済的自由とは、収入より支出が少ない状態が続くこと。
そのためには、毎月の支払いに縛られない仕組みを作ることが重要です。
住宅ローンを組むと、返済が数十年続きます。
家賃より安く見えても、固定資産税や修繕費を含めると実質負担は増えることもあります。
一方、賃貸なら家を変える自由があり、ライフステージに応じて住居コストを最適化しやすいのが強みです。
実際、FIRE(経済的独立・早期リタイア)を目指す人の多くは「可変費化」を重視しています。
家もその一部として柔軟に考えることが、自由への近道です。
「資産としての家」は本当に得か?
「持ち家=資産」という考え方は、昔の常識に近いかもしれません。
人口減少と空き家の増加が進む日本では、住宅の価値は下がる傾向があります。
ローンを払い終える頃に、家が老朽化して資産価値がほとんど残らないことも。
たとえば、3,500万円のローンを35年で返済した場合、利息や維持費を含めれば総額5,000万円近くになることもあります。
この金額を「住むための費用」として割り切れるなら問題ありませんが、投資としてはリターンが見えにくいでしょう。
ただし、心理的な“安心感”を得られるのも事実です。
「家を持つ」ことで、生活の拠点を安定させ、老後の住居不安を減らす効果は大きいです。
つまり、**数字では測れない“心の資産”**としての価値をどう捉えるかが分かれ道になります。
自由を基準に選ぶという考え方
どちらを選ぶにしても、目的は「安心して暮らす」こと。
もしあなたが場所や働き方の自由を重視するなら、賃貸が向いています。
反対に、家族との暮らしや地域コミュニティを育てたいなら、持ち家が合うでしょう。
大切なのは、“どちらが正しいか”ではなく、**“自分にとっての自由がどちらにあるか”**を明確にすることです。
経済的自由は、所有よりも「選択できる状態」にあること。
その視点を持てば、どちらを選んでも後悔しない人生設計ができます。
まとめ
住宅ローンも賃貸も、それぞれに「安心」と「自由」のバランスがあります。
経済的自由を目指すなら、どちらか一方にこだわるより、人生の変化に合わせて“住まいの形を柔軟に選べる力”を持つことが大切です。
家は「買う」ものではなく、「人生を支える道具」として使いこなす時代。
次に引っ越すとき、または家を検討するとき――
「この選択は、自由を広げるものか?」と一度立ち止まって考えてみてください。